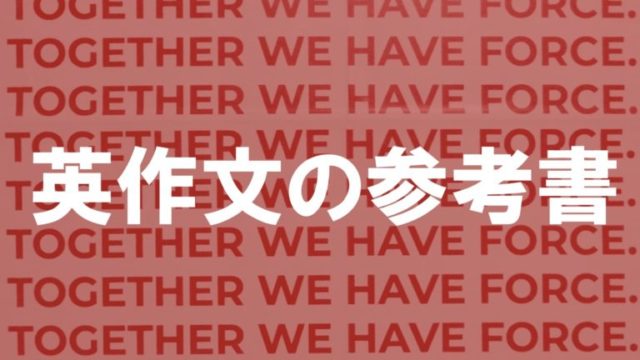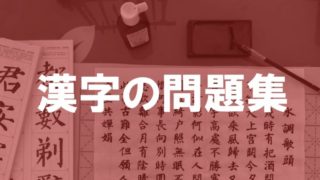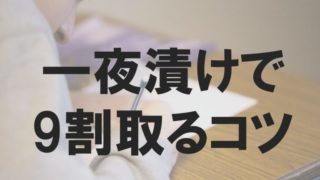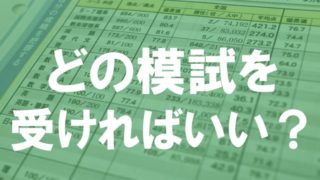化学に限らず、受験勉強で大切なことは『何を』、『どれだけ』勉強したかです。
このうち、どれだけ勉強したかということについてはあなたの頑張り次第でどうにでもなります。
1日に10時間やったらそれだけ力がつくし、3時間しかできないならそれはそれだけの学力しかつかないということです。
しかし、「何を」すればいいかは自分ではわからないことが多いです。身にならない参考書を使っていては1ヶ月後には大きな差になって現れます。
そこで、今回は僕が受験で使っていたものや友人が使っていたもの中心に化学・化学基礎でおすすめの参考書や問題集を集めてみました。
ここに挙げたものはどれも間違いなく「良い」参考書と言えるはずです。ぜひ参考書選びの参考にしてみてください!
目次(クリックでジャンプ)
良い化学の参考書って?
紹介をしていく前に、良い化学の参考書の条件をいくつか挙げておきます。自分が使っているもので確かめてみてください。
1つは、どの分野も満遍なく問題があるものです。
例えば理論にページ数の半分以上を割いていて、有機と無機はほんの少し、とい言ったような参考書をたまに見かけますが、こういったものは有機無機の補強が必要になってくると思います。(配点的にはわからないですけど…)
もう1つは、しっかりと補足説明がしてあることです。化学は物理と違って暗記で取れる問題もかなりある代わりに、覚えることが多いです。
1つの問題で1つの知識を身につけていたのではコスパが悪すぎます。
例えばいまはこうだけど別のパターンだったらこっちになるよね!というような解説がなされていたら非常に丁寧で勉強していくうちに自然と力が身についていくでしょう!
- 分野に限らず問題がたくさんある
- 補足説明がしっかりされている
これらの特徴を頭に入れつつ、おすすめの化学の参考書を見ていきましょう!
化学が苦手な人向けの参考書
まずは、化学が苦手な人向けの初心者レベルの参考書を紹介します!
化学が苦手だよ、と言う人は、こうした入門書に手をつけてみて、「化学の面白さ」を感じてから次のステップに進むようにしてみてください!
岡野の化学が初歩からしっかり身につく
(2024/04/24 13:46:51時点 Amazon調べ-詳細)
- 化学の初歩の初歩の理解が身につきます!
学校の勉強についていけない人や、先生が何を言っているのかわからないという人にまず手をつけて欲しいのがこの「岡野の化学が初歩からしっかり身につく」です。
このシリーズは、もともとは東進から出版されていた「化学を始めからていねいに」(通称 はじてい)の改訂版みたいです。この本の執筆者の岡野先生は東進の講師みたいですね。
この本の良いところは講義形式で本当に基礎の基礎だけをわかりやすく解説してくれるので、読み物のように呼んでいれば大体授業内容くらいを理解できてしまうところです。
ただし本当に基礎的な内容に終始しているので、問題はほとんどないと言ってもいいくらいに少なく、難度も低いです。なので問題集というよりも参考図書といった感じ。
まず授業についていけない人や化学が嫌いな人の窓口としておすすめしたい一冊です。
らくらくマスター 化学基礎・化学
(2024/04/23 21:18:17時点 Amazon調べ-詳細)
- 化学を問題を解きながら肌で身につけられる!
問題集としては僕が見た中では最も優しい部類のものです。
この程度の問題なら、化学が苦手な人でもスラスラ(とまではいかないかもしれないけど)解けちゃうのではないかなと思います。
化学に限らず、参考書が苦手な人はいかんせんむつかしい問題を時過ぎてるような気がします。問題をみて、うーんと考えて、解くみたいな。でもそうしていると時間も結構かかるしストレスもたまります。
だからそういう人はまずこういった簡単な問題集を何か一冊やり遂げてみるのがいいかなと思います。
例題が100問と演習問題が200問あってボリュームもなかなかで、らくらくとはいかないかもしれませんが、1撮やりきると確実に実力がつくと思いますよ!
鎌田の化学基礎をはじめからていねいに
(2024/04/23 21:18:13時点 Amazon調べ-詳細)
- たった3日で基礎的なイメージを身につけることができる
参考書界隈で大変有名なのが、このはじめからていねいに、通称「はじてい」シリーズです。
帯にも書いてあるように、ゼロから始めて3日くらいで基本的なイメージをつかむことができるので、入門にもってこいです。
化学でいえば、反応式をただ単に覚えるだけでなく、「どうしてその反応をするのか?」などをしっかりと解説してくれます。
なので、これから詳しく勉強しようと言う人にざっくりとした理解をもたらしてくれます。
図や写真もたくさんあるので、センター試験の対策としても有効ですよ!
高校とってもやさしい化学・化学基礎
(2024/04/24 13:46:51時点 Amazon調べ-詳細)
こちらは、「とってもやさしい」シリーズとして知られている参考書です。
僕は使っていないのですが、文系の化学をやっていた友達が使っていたということで紹介します。
シンプルで最低限のことだけが書かれているのに、「授業がわからなかった僕でもわかる」と、その友達は言っていました。
内容的にそれほど詰まってはいないのですが、簡単に1周できるので全体像をつかむのにはいい参考書だと思います。
宇宙一わかりやすい高校化学
「くま」や「ハカセ」などが登場するので、パッと見ると「参考書みたいな絵本かな?」と思うかもしれません。
でも、実際は逆で、とてもとっつきやすい参考書なのです。
イラストや図が豊富にあるので、化学が苦手な人にも直感的にわかりやすい内容になっています。
しかも、重要な点は簡単でわかりやすいのに、エッセンスが詰まっている点です。
楽しんで化学を覚えたい、と言う人はぜひやってみてください!
教科書レベルの問題集・参考書
続いて、教科書の確認問題〜発展問題あたりの難易度の参考書・問題集です。
何事も基礎が大事なので、点数が伸び悩んでいる人がいたらこの辺りを徹底的に復習してみると良いでしょう。
セミナー化学
(2024/04/23 21:18:18時点 Amazon調べ-詳細)
- 問題が多いので定着しやすい!
セミナー化学、化学基礎は学校の副教材として僕が使っていたものです。分量がとにかく多く、難易度にもかなりの幅があったイメージです。
こういう、学校で配られる参考書は誰が使ってもそれなりになるように問題の難易度が広いことが多いです。
なので自分の実力にあった部分だけやったり、テストの範囲だけ解いたりしないと余計に時間がかかってしまう可能性があります。
いい点は、解説がしっかりしているところです。しかも先生に聞きにいけばこの参考書の問題だけはとても丁寧に答えてくれたので勉強になりました(もちろん他のも教えてくれましたが…)。
チャート式シリーズ新化学
(2024/04/24 13:46:53時点 Amazon調べ-詳細)
- チャート式になれた人は使いやすい!
数学で「チャート式」を使っていて、化学でもやってみたいという人はこちらがおすすめです。世にいう化学のチャート式です。
フルカラーで、かなり詳しい部分まで載っているので、教科書のように何かあったら見直すのに最適です。
化学は図や表の問題が出たり、計算にかなり3次元的なイメージを必要とする問題があるのでこういった本が一冊あると何かと便利です。
30日で完成 センター試験対策 化学基礎
(2023/08/15 01:37:02時点 Amazon調べ-詳細)
- センター化学基礎対策にバッチリ
- ゴリゴリとチャートをやりたい人にオススメ
同じチャート式なのですが、こちらはセンター試験対策に特化しています。
化学基礎とはいえ、それなりにレベルが高くなるので「苦手な人向け」の参考書を終えた人や、化学がそれなりにできる人に手を出してほしい参考書です。
30日で完成すると言っていますが、実際はもうちょっとかかるかもしれません。
それでも、1冊をやり終える頃にはセンター化学基礎の土台ができるているので、このチャート式から赤本に進んでもいいかもしれません。
※化学基礎ではなく化学を受ける人は、もう2冊くらいやってから過去問にチャレンジしてみるといいでしょう。
化学 一問一答
(2024/04/24 17:27:55時点 Amazon調べ-詳細)
- センター試験に必要な暗記はこの1冊で十分!
- 知識が足りない人はこれをやると良いです
東進ブックスから出版されている「一問一答シリーズ」の化学です。
化学は暗記することが多いと前に書きましたが、暗記物が一冊に詰まっている本というのはなかなか少ないです。(というかこの本以外知りません)
なので何か1冊持っておくと隙間時間に勉強したり、自分が暗記できていない範囲がわかっていいでしょう。
赤シートがついているので、問題を隠して、口頭で答えて、覚えてないところをチェックして、を何週も繰り返せば1ヶ月くらいでマスターできるようになりますよ。
化学の暗記は直前にすればいいやという生徒も中にはいますが、暗記することはたくさんありますし、特にレベルが上がってくれば暗記していないものともう頭に入っているものを仕分けるのだけでも時間がかかります。
合否は1点で決まることも珍しくありません。それが暗記だとしたら…悔やみきれませんよね。なので早めの対策をおすすめします。
入試に出る化学反応式 まとめとポイント
(2024/04/24 13:46:54時点 Amazon調べ-詳細)
- 化学反応式をまだ覚えていない人
この参考書は、タイトル通り「入試に出る化学反応式」のまとめとそのポイントを解説してくれます。
化学反応式は、化学の中でも “最重要” な暗記です。
なぜかというと、化学反応式を覚えていないと理論化学・無機化学・有機化学のどれも点数を取れないから。
逆に言えば、化学反応式を正確に覚えているならば、それぞれの分野の基礎は完璧にマスターできているということです。
反応式は早めに覚えておくことに越したことはないので、是非今のうちに手を打ってみてください!
チョイス新標準問題集
(2024/04/24 13:46:55時点 Amazon調べ-詳細)
- 基本問題を集中して取り組みたい人にオススメ
- ドリルをゴリゴリに解いていく感覚
チャート式化学やセミナー化学と同じように、問題集がゴリゴリですが、基本問題をしっかりと扱っている印象です。
各セクションが、「基本まとめ」「演習」「演習の解説」「実戦問題」「解答・解説」に別れていて、それぞれを進めていくと力がついている、という構成になっています。
オーソドックスですが、問題が多すぎず少なすぎずちょうど良いので時間的にも余裕をもって終わらせることができると思います。
すぐに大学の入試問題をときたいけれど、レベル的にもう1ステップ踏みたい人にオススメです。
坂田アキラの 化学基礎の解法が面白いほどわかる本
- 基本問題を解いていきたい人
- 高校1,2 年生で基礎からやっていきたい人
この『化学基礎が面白いほどわかる本』は個人的には物理でいうところの『物理のエッセンス』と同じようなものだと思っています。
なので、一言で言えば「圧倒的に始めの1冊に向いている」ということです。
基礎的な問題が多く、それでいて化学基礎の基本的な理解であったり解説だったりが全範囲、レベル的にもしっかりと網羅しています。
問題点を挙げるとすれば、問題の数がそこまで多いわけではない点です。
なので、他の問題集(例えば、『らくらく化学マスター』など) と合わせて使っていくといいでしょう。
Amazon のレビューにもありましたが、このレベルの問題の解法がパッと5秒以内に浮かぶようになれば、ここから先はかなりスムーズに進んでいくと思いますよ!
今まで紹介してきた参考書・問題集は1つ1つをていねいにやっていくことをおすすめします。何冊もやる、というよりは1冊をじっくりと読み進めてみてください。
センターレベルより上の参考書
いよいよセンター試験のレベルを超えて、私立の化学や2次試験対策用の参考書を紹介していきます。
基礎問題精講 標準問題精講
(2024/04/23 21:18:15時点 Amazon調べ-詳細)
- 基礎・標準ってあるけど、結構レベルの高い参考書!
数学や物理でおなじみの基礎問題精講、標準問題精講です。
旺文社から出版されていて、理系の化学の参考書だとまさにコレという感じです。とりあえずセンター試験を8割取れるレベルになったら基礎問題精講やってみようかという感じ。
標準問題精講は難関大の問題も含まれ始めるのでいきなりはきついかもしれないです。ここでいう標準は入試問題の「標準」なのであんまりあてにしてはいけません。
問題量は80問と少なく見えますが、一問一問のレベルが上がっているだけに解くのも解答・解説読んだりするのにも時間と根気が必要になってきます。心して取り組んでください。
また、解けなかった問題は絶対にそのままにしないこと。同じ問題が入試に出たら満点取れると自信を持っていうことができるまで解き直してください!
理系標準問題集
(2024/04/24 13:46:57時点 Amazon調べ-詳細)
- 入門書が「簡単」に解けるけど入試問題が「難しい」と思う人におすすめ!
通称、理標と呼ばれています。標準的な問題が網羅的に取り上げられています。
一説には、解答作成者が5人いて解放がそれぞれバラバラだという説があるのですが、実際にはどうなんでしょう?
使っていた友達によれば、センター試験のような標準的な問題は解き終えて、でも志望校の過去問や模試では歯が立たないという人におすすめの一冊だそうです。実践レベルへの橋渡しとしてなんとも良さそうですね!
重要問題集 化学
(2024/04/23 21:18:19時点 Amazon調べ-詳細)
- 問題数が豊富
- 毎年、受験の傾向をしっかりと捉えている
- 標準的な問題が揃っていて、応用が効く
やってきました!ご存知(なかったらごめんなさい)の重問です。
僕は数学でも物理でもこの重問を紹介しましたが、化学でも紹介します!数研出版から毎年改定出版されていて、最新の傾向を基にした300問近い良問が載っています。
今ではおそらく買っている人が最も多い化学の参考書ではないでしょうか?
最初にいった良い参考書の条件の、「網羅性・補足説明」もあり、問題数も申し分ないです。
ここで目にしていないパターンの問題は入試には出ない、もしくは出てもほとんど差がつかないと思ってもらってもいいかもしれません。
東大、京大は別にしてもそれ以外の大学はこの重要問題集を参考にしていればまずまあ違いなく合格ラインまで学力を伸ばせると思うのでぜひ頑張って勉強してみてください!
化学 入試の核心
(2024/04/23 21:18:16時点 Amazon調べ-詳細)
- 入試の核心に触れることができる参考書
- 是非、何周もしてもらいたい
化学に限らず、入試で高得点をとる近道と言えば、ズバリ「頻出問題や典型的な問題の型を覚えて、それを頭に叩き込む」ことです。
この『入試の核心』は、それを可能にしてくれる参考書です。
大学入試の化学に必要になる7つの力を、22の問題を解くことによって身につけようという、なんとも贅沢な1冊です。(もちろん、練習問題は100題ありますが)
この問題を繰り返し解いて、流れを頭に作っておくと類題がでた時に正確に解けるようになります。
この回路を頭に作りたい人、入試の核心に触れたい人にぴったりの参考書です。
二見の化学問題集 ハイクラス編
(2024/04/24 13:46:57時点 Amazon調べ-詳細)
- 表紙のキャッチーさにいい意味で裏切られる
- 難易度の高い問題でも、わかりやすい
表紙がキャッチーだし、何と言っても「東進ブックス」の参考書なので、入門書だと思って購入して失敗する人が続出する参考書です。
最初に言っておくと、はっきり言って難しいです。
普通に東大や京大の過去問題が出てくるし、オリジナル問題もユニークで見たことないようなものばかりです。
でも、「難関大学志望向け」としないでここで挙げた理由はただ1つ。
それは、是非とも多くの受験生に手に取って欲しかったからです。
問題も良問が多いし、解答もとてもわかりやすいです。これをやっている人は、かなり強いんじゃない穴、と思います。
このレベルが解けると化学が得点源に変わるので、ライバルに差をつけたい人にもおすすめです。
難関大志望向けの参考書
以下、難関大志望の人向けの参考書です。
この辺りになってくると、化学だけの点数を伸ばすのか、それとも他の教科に時間を割くのかが需要になってきますね!
化学の新研究
(2024/04/24 13:47:01時点 Amazon調べ-詳細)
- 大学に入っても使うことのできる参考書です!
難関大向けといえば、コレ!という感じで名が知られている化学の新研究です。
高校の範囲を超え、大学で習う範囲にまで言及しているので無茶といえばかなり無茶のある参考書です。
しかし、化学を勉強する上で「なぜ?」と疑問に思うことはとてもいいことで、それを突き詰めて考えていけばどこで習う範囲かなんてのは小さなことです。
だから大学受験というよりは、化学が好きだからという理由でもっている人が多いかもしれません。
実際、京大の工業化学科の友達に聞くと、化学の新研究を使っていた人というのは結構たくさんいました。
大学の範囲もやっておいてよかったという人もいたのでか化学好きの人はぜひ手をつけてみてはいかがでしょうか?
実力をつける化学
(2024/04/24 13:46:58時点 Amazon調べ-詳細)
- 問題のレベルが一様に高い参考書!
実力をつける化学はZ会から出版されている割と新しい参考書です。あまり知名度のある参考書ではなく、僕も友人から教えてもらうまでは知りませんでした…
かなり難易度の高い問題ばかりを取り扱っているらしく重問を終えた人がやるといいレベルとなっています。
化学が得意な人や、化学で他の人に差をつけたい人なんかは解いてみてもいいんじゃないかと思います。
化学は参考書が難しくなればなるほど解説がちんぷんかんぷんになるのが困ったもんだと思っていましたが、この本は流石のZ会クオリティなのでご安心を!
新理系の化学問題100選
(2024/04/24 13:46:59時点 Amazon調べ-詳細)
- 東大・京大・東工大以外の人は解く必要なし
先ほどの『実力をつける化学』がZ会クオリティだとするならば、こちらは駿台クオリティ。
はっきり言って、化学の参考書の中でも最も難易度の高いものだと思います。
対象としている受験生はおそらく「東大・京大・東工大」志望の生徒のみ。それも、「化学で大量得点がほしい!」と思っている人だけだと思います。
ただ、難しいにも関わらず解説が丁寧なので、このレベルの人なら解説を読めば理解できると思います。
受験本番までに全部の問題を解くのはなかなか大変だと思うので、苦手な分野だけでもまとめてやっておくと周りとかなり差をつけられると思います!
おまけ:全ての受験生に
これから紹介する「赤本」と「模試の復習」は全ての受験生にやってほしい参考書です。
今まで紹介してきた問題集なども、この2つをやってこそです。
赤本 (自分の志望校に最適なものを選びましょう)
(2024/04/24 16:18:20時点 Amazon調べ-詳細)
ここまで色々な参考書をおすすめしてきましたが、何と言っても忘れてはいけないのは志望校の過去問、つまり赤本です。
赤本はただいい問題がたくさんある参考書なのではなく、過去問です(当たり前ですが)。なので本番のリハーサルとして時間配分や解答作成の予行演習にもってこいなのです。
しかも、過去の問題から志望校の問題の傾向が見えれば対策のしようもあります。例えば京大はここ数年有機がやたら難しい問題が多く、無機化学に時間を割いて点数を狙った方が効率がいいぞ!という具合です。
また、化学と物理合わせて180分の試験なんかは、どちらの科目に何分かけるかもかなり重要になってきます。
そんなこんなで過去問は超重要です!まずは過去五年分の問題くらいはきっちり解けるようにしておきましょう!
また、東大、京大をはじめとする難関校では○大の化学25ヶ年のように化学の問題だけを25年分集めた参考書なんかも出版されているので興味があったらやってみるとより傾向がわかると思います。
模試の過去問
(2024/04/23 18:48:41時点 Amazon調べ-詳細)
模試の復習はしっかりしていますか?赤本の問題はいわば過去に出題されてしまった問題なのでもう試験に出る確率は低いですが、模試の問題は試験を想定して作ってあるので実際に試験に出ることもあるんですよ!
特に化学の問題は暗記問題もあるのでそういった問題はセンター試験などでは的中したりします。
また、記述問題や計算問題も模試の頻出問題を扱っているので復習しておくことは大切です。一度解けなかった問題を解き直すことで自分の実力の伸びを実感できたり、新たな苦手を発見できます。
問題は解きっぱなしというのが1番良くありません。しっかり復習し、次に繋げましょう。
最後に
最後の方は、「お前は私のチューターか!」とツッコミたくなったかもしれません。
でも、チューターさんも、もちろん僕もあなたのためを思っていっているのでじゃけんにしてはもったいないですよ。
この記事で化学のおすすめの参考書を21冊あげましたが、どれか使えそうなものや興味をもってくれそうなものが一つでも見つかれば幸いです。
1度いい参考書がみつかったらあとは初めに言った通り、あなたがどれだけ勉強に時間と熱意を割けるかです。頑張ってください!応援してます!