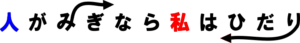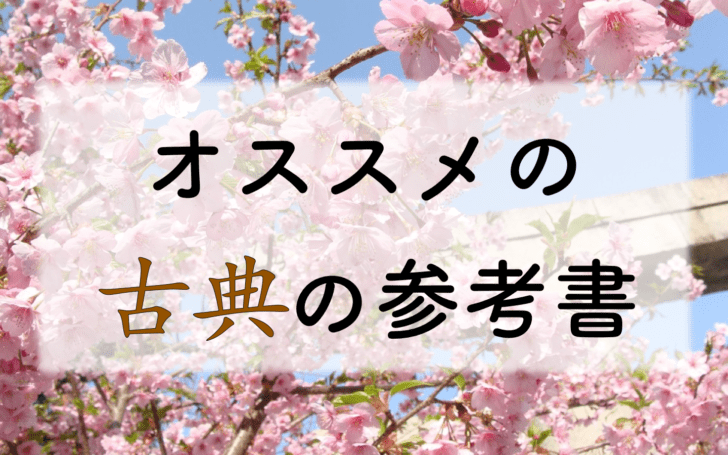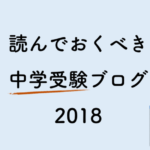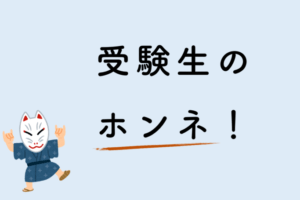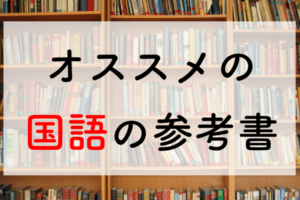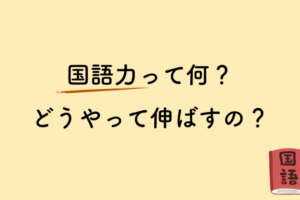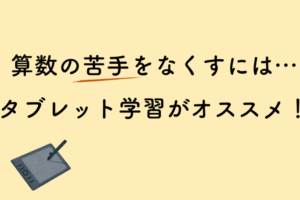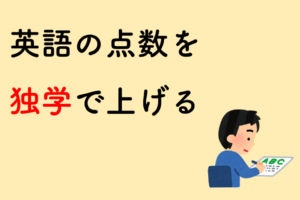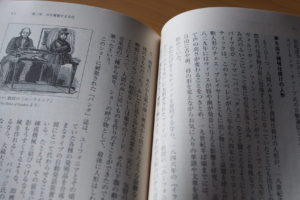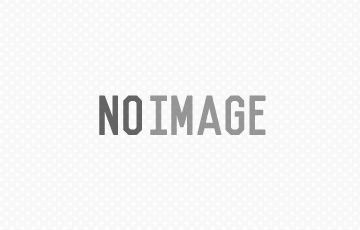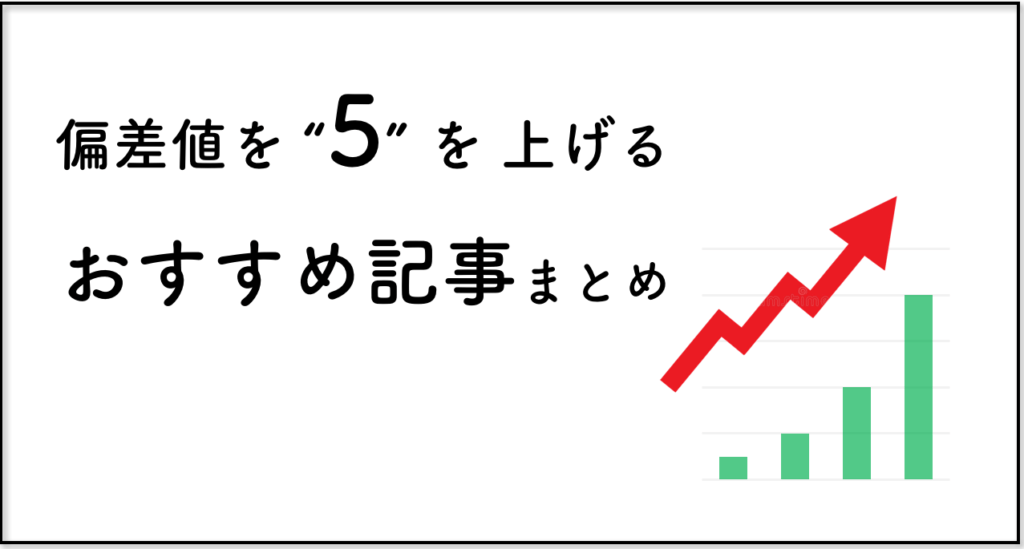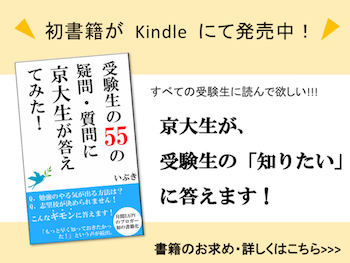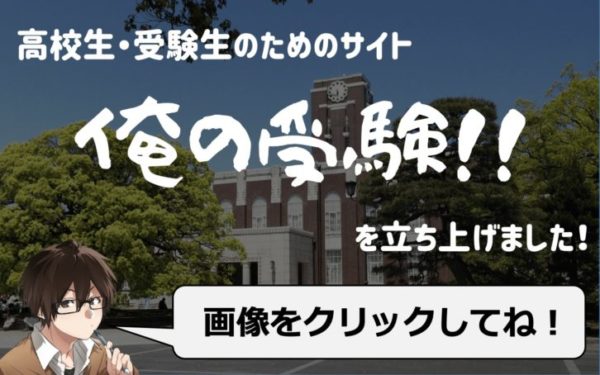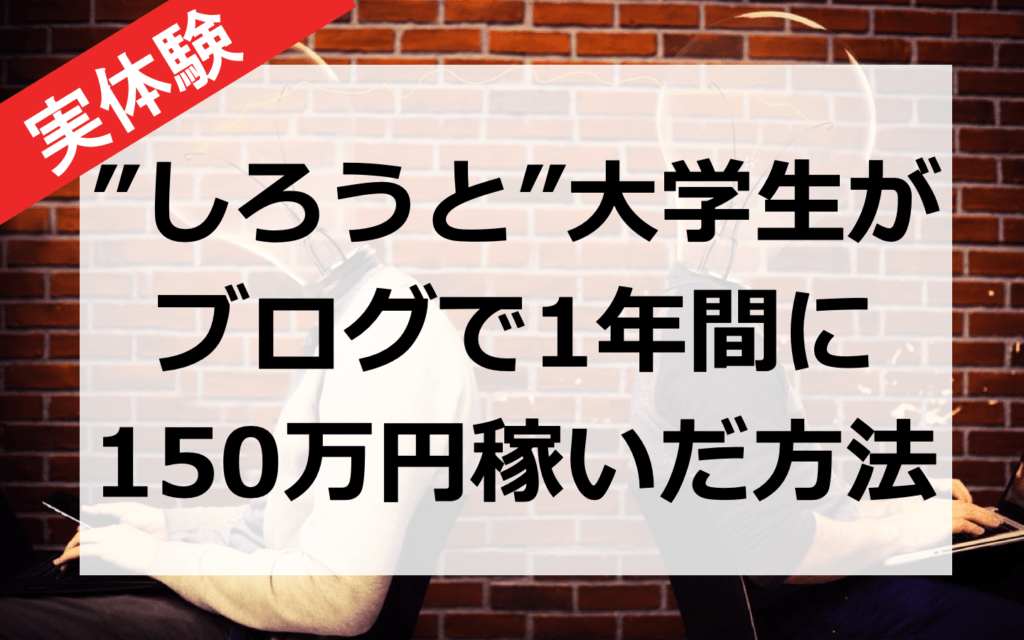数ある受験科目の中で、最も後回しにされやすく、そしてそれでもなんとかなってしまう科目といえば…そう、「古文」です。
それはなぜかというと、みんな「なんとなく解けてしまう」からです。
問題の大体の内容は掴めてしまうので、こっちであってるかなー?と思った選択肢がたまたま当たってたりします。
しかし、もちろんそんな勉強しかしていないと本番で大コケしてしまう可能性があります。なんとなくで点が取れてしまうということは、なんとなくで点を落としてしまうのです。
では、どうすればいいか?
勉強しましょう。当たり前ですが…
特に、今まで後回しにしてしまっていた人なんかは、ちょっとやるだけでグンと成績が上がる場合もあります。
ということで、今回は古文のオススメ参考書を、勉強して欲しい順番にまとめてみました。
どの参考書も、僕が実際に使っていたものと、周りの友人が使っていたものを中心に紹介していきます。
古文はやれば伸びるし、漢文の基礎になるので個人的には点数稼ぐのにコスパのいい科目です。
僕はセンターで国語192点(古・漢は満点でした)とれたのでこれらをやり込めばあなただってきっと大丈夫!
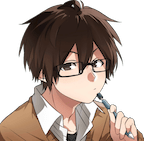
一応、次のようなジャンルに分けて紹介していきます。
- 古文単語・古文常識
- 古文の文法
- 古文読解
- 過去問・模試など
- 和歌などのポイントごとの問題集
目次 (クリックでジャンプ)
古文単語・古文常識はキソ!
まずは単語がわからなければ話になりません。古文はほとんど「外国語」みたいなものです。
スラスラ意味をとっていくためにも単語の知識は必須となります。
特に、テストで狙われやすいのは現在でも使われている言葉で、意味が違うもの。これらは勉強しないとわからないものが大半です。
また、古文を読む上では歴史的な背景や常識が必要になってきます。ある程度のものは最初にわかっておいた方が良いでしょう。
読んで見て覚える重要古文単語315
学校の副教材として買わされた 買ったものですが、質、量ともに受験はこれ一冊で十分!と言えるほどの単語帳でした。
他の単語帳はそれぞれ単語のチョイスに偏りがあったり、単語数が極端に多かったり少なかったりするのですが、これはちょうどピッタリくらいです。
個人的には、テストに出やすい「敬語」がまとまっていたり、古文常識がちょいちょい挟まっていたところがポイント高いなと思いました。また、本のタイトルどうりイラストがたくさんあって覚えやすい。
「単語城、何にしようかな」と悩んでいる人に自信を持っておすすめできる一冊です!
マドンナ古文単語 230
古典界の、いや受験界の”マドンナ” といえばこの方、荻野文子先生の古文単語帳です。
こちらは先ほどの読んで見て覚えるよりも語彙数は少ないですが、まあギリギリかなというくらいの量です。
このマドンナ古文は、古文文法や長文など色々な他にも色々なシリーズがあるので、「他にマドンナを使ってみて、悪くなかった」と思った人や、「講義形式の参考書の方が肌に合う」という人は使ってみるといいと思います。
また、マドンナ古典常識 231は、隙間時間などに、古典常識を知るためにかるーく読むのに適しています。今はブック○フとかにも転がっているかもしれないので探してみては?
速読 古文単語
この『速読古文単語』は、古文単語を文章そのままに覚えてしまおうという参考書です。
この参考書のいいところは、ズバリ「古文の文法などもそのまま覚えることができる」ということです。
なので、他の参考書より、より効率的に単語を覚えることができます。
しかも、その文章を覚えていると勝手に古文常識が身についてしまうというスグレモノ。
なので、例えば上の2冊の単語帳を全部やり終えてしまったけど、まだ単語に不安が残る、という人におすすめです。
ただ、デメリットとしては、古文が苦手な人が使ってしまうとチンプンカンプンかもしれないということ。
ある程度自信のある人は使ってみてください!
望月 光の古文単語333
この単語帳の良い点は、「単語を意味から暗記できる」ところです。
単語ひとつひとつの成り立ちや派生語を詳しく解説してくれるので、評判通り覚えやすい単語帳になっています。
しかも、単語チェックシートなども付いてくるので、他の単語帳ではダメだったけれど、これなら大丈夫、という人も多いはずです。
とことん暗記にこだわって作られているので、暗記が苦手な人はぜひ試してみてください!
古文単語ゴロゴってどうなの?
古文単語ゴロゴ は、ややこしい古語を、語呂合わせで楽しく覚えられる単語帳として誰しも一度は見たことあるかもしれません。
この参考書については、「覚えやすくていい」とか「こんなもの使っては成績は伸びない!」とか色々な意見が出ていました。実際のところどうなのか、と高校生にも幾度となく質問されています。
個人的な意見を言わせてもらうと、
と思いました。
確かに、語呂合わせなのですが内容とごろがほとんど合致していません。古文になれるために使うのは有効かもしれませんが、受験という観点で見たときに”自信を持って” オススメできるかというと… です。
最初にも言った通り、古文は外国語だと思いましょう。そして、古文単語は英語で言う英単語です。
英単語を覚えなきゃ英語が読めないのと同じように、古文単語も覚えないと問題は解けるようになりません。
辛くてもつまらなくてもしっかりと暗記をするようにしましょう!
古文文法は、正確に確実に
単語の次は、文法です。古文文法は、
これは何活用の動詞かを答えなさい
という問題の対応とともに、文法単位での正確な文章の読解に役に立ちます。
特に、古文を和訳させる問題などはこの文法の理解ができるかどうかの加点式が多いです。
一旦覚えてしまえば忘れにくいので覚えるなら早めがいいですよ!
富井の古典文法をはじめから丁寧に
こちらは、古典初心者~センター試験レベルまでの参考書。受験業界では有名な「ハジテイ」シリーズの1つです。
本当に基礎の基礎からやってくれるので、古典を始める人や苦手な人にはおすすめの1冊です。
学校で配られたりするプリントや他の文法教材と違って図やイラストなど読み手を楽しませる工夫もあります。文法なんてやりたくもない!という人にこそふさわしい一冊です。
古文文法講義の実況中継
こちらは、受験生におなじみの実況中継です。この本のいいところは、ズバリ「講義形式」であるということ。
なので、初心者の人もとっつきやすく、また「暗記だけ」になることなく
- どうしてその文法事項が大事なのか?
- どうやったらこの助詞を暗記できるのか?
というような事が、(関西弁で) 懇切丁寧に書かれています。
ただ、やはり講義形式なので演習問題の量は少なめ。なので以下に紹介するドリルなどと併用して進めると理解しながら問題量もこなしていけるようになるでしょう。
ステップアップノート30 古典文法基本ドリル
初めから丁寧に より少し難易度が高いのが、このステップアップノート30 です。癖がなく、基本的な文法は全て網羅されています。復習用、確認用にも便利。
文法はこれをやればいいと思っているのですが、一つの難点はやっぱりあんまり面白くないことです。
もし学校の授業で文法をしっかりやっているのならいっそ飛ばして問題の中で解いていくのもありだと思います。
特に、センター試験ではよく問われる文法が決まっているので、文法に時間をかけたくないという人は、センター古典の文法問題だけを20年分くらい解いてみたらいいのではないでしょうか?
古文 ヤマのヤマ
受験生なら三羽先生の『漢文ヤマのヤマ』は知っているかもしれませんね。
この参考書は、その古文バージョンです。
試験に出るような文法だけを集めたので、「手っ取り早く点数を上げたい」人には最適の文法書だと言えるでしょう。
ただ、逆に言えば早慶や東大・京大・一橋を目指すような人であればもう1ランク上の文法を押さえていないといけません。
わかりやすさを取るか、質を取るか、というのは常に今の自分の実力と照らし合わせて考えてみてください!
古文 高校中級用 42 (発展30日完成シリーズ
ドリル形式としてガシガシ解いていくのには、この問題集もおすすめです。
内容としては、中級の問題がどさっとあるだけ。変な話、面白みのあるものではありません。
ただ、こうした問題を解かなければ記憶に定着していきません。僕が見たときには中古で1円から売っていたので、買ってぜひやってみてください!
文章の読解は古文の花形です
ここまできたら、いよいよ古文の文章を読んでいくといいと思います。単語、文法の要素が頭に入っている人はセンターレベルの問題ならもうすでに解ききる能力があると思います。
なので、そのままセンターなどの過去問に入ってもいいのですが、時間があるのならもう少し読みやすい文章から入っていくとスムーズに次につながります。例えば、古文の場合は
- 主語が省略されやすい
- 敬語などで主語を判断する
- 場面がコロコロ変わったり、主人公が変わったりする
など現代の文章と違うところが多く合って戸惑うことも多いです。これらが不安な人は読解のワンステップを踏んでおいたほうが無難です。
全レベル問題集 古文
僕が受験をしたときにはなかった問題集ですが、最近になって受験生に人気だということで紹介したいと思います。
この『全レベル問題集』は古文だけでなく数学や英語などでも出版されている参考書で、レベル別に3冊にわかれています。
おすすめなのがこの「センター試験レベル」です。
この辺りの問題を、数多くこなして身につける事が上達への近道だと思います。
解説が丁寧でわかりやすいので、原則としては全部を丁寧にこなしていくことをお勧めします!
富井の古典読解をはじめから丁寧に
先ほどの富井先生が再び登場です。読解のポイントを押さえつつ、割とあっさりしたボリュームになっています。パパッと読みたい人、時間をかけたくない人にはいいと思います。
心構えみたいなところを中心に解説しているので、これだけでは練習量が足りませんが、それは後々問題集で実践を積んで行けばいいと思います。
講義形式は本当に先生の 合う・合わない があるので、富井先生の初めからシリーズが気に入ったという人は読んでみるといいかもしれません。
古文上達 基礎編 読解と演習45 文法理解から応用まで
先ほどとは違って、問題を解いていきながら学んでいくタイプの参考書です。問題集といっても差し支えないかも。
受験用の古典の教材として高い評価を受けています。
読解だけでなく、単語や文法などの基本的なことも聞かれるので今までの確認や腕試しとして解いていくこともできます。
自分がどれくらい解けるのか、どこを復習し直せばいいのかも一発でわかるので時間がある人は是非解ききりたい1冊です。
はじめの一歩 古文読解問題集
受験生に1つ知っておいて欲しい事があります。それは、「駿台文庫から出ている参考書にある “はじめの” とか “入門” とかいう言葉は信用しない方が良い」という事です。
この本もまぁかなりの難易度で、全問記述式になっています。
その意味で中級、上級向けの参考書と言えるでしょう。
ただ、記述がメインということもあって国公立や私大文系の受験者の人にとっては受験勉強の最後の方まで使えてかなり重宝すると思います。
誤解をしないように言っておくと、駿台文庫の参考書は良書ぞろいです。ただ、講師たちの求めている難易度が他の予備校と比べて若干高いのかな、ということです。
問題集・過去問は受験生の基本!
さて、ここまできたらあとは問題を解くのみです。
志望校がすでにはっきり決まっている人はその大学の過去問や類似問題、まだ決まってない人やもっと広くいろんな問題に触れたいという人は問題集をやるといいでしょう。
古文 入試精選問題集
河合塾の入試精選問題集は、英語や数学では「プラチカ」という名前で知られている参考書シリーズです。入試問題の中から、基礎的な問題事項や頻出の出題形式などを集めた問題集です。
国公立2次や私立の入試対策用の参考書なので最後の方の問題はセンター試験だけで良い人にとっては少し難しいかもしれません。ただ、ポイントを押さえた記述ができるようになると逆に選択肢を絞ったりするのも上手くなるのでやっておく価値はあります。
全体的にレベルが高いですが、いわゆる良問・典型問題が多いので復習は必ずやるようにしてください!
古文 基礎問題精講
こちらも、先ほどと同様に「入試問題の中からいろいろなパターンの問題を選び抜いた」タイプの参考書です。
どちらか好きな方をやってみるといいと思います。
ただ、こうした参考書には注意が必要で、それは「志望校の対策の方がはるかに優先しなければならない」ということです。
だから、入試まであと2ヶ月切っていているならば、迷わずに志望校の赤本とその解き直しをやるべきです。
自分には今何が必要か、ということをしっかりと把握しながら勉強を進めてみてください!
中堅私大古文演習
タイトルどうり、中堅私立受験用の演習問題がまとまった1冊です。漠然と「私立文系」を考えている人は手に取るべきです。
あとでもう少し触れますが、私立は少しエグめな文法問題や文学史なんかが狙われたりすることがあるので対策が必要です。
一番いいのは過去問ですが志望校が決まらない人はこれをやっておけばまず間違い無いかな。
問題毎の解説がとてもしっかりしているので一人でも勉強しやすいです。やっていて、「あ、つまずく」と思ったら一度復習しましょう。
センター過去問
センター試験がある人は、センターの過去問を解くのがいいと思います。本試験と予備試験を合わせれば問題量も十分ですし、解説もちゃんとしています。
注意としては、問題が解ければいいや!という姿勢をするのは本番前ギリギリになってからにしたほうがいいということです。例えば、解説の和訳と違う解釈をしていたとしたらそれをほったらかしにしておくのではなく、
- どこで読み間違えたか(単語? 主語? etc…)
- 新しく得た知識で覚えることはないか
- 復習するポイントはないか
などを常に気にしてみるといいと思います。
間違えたポイントだけをノートにまとめておくのもアリ!
赤本
センターの他に、国公立や難関私大を受ける人は、上に挙げたような「〇〇の国語 25年」など教科ごとにまとまったシリーズがあるので対策をとっておくといいでしょう。
2次試験には筆記問題も多く、自分一人で学習することが難しくなるかもしれませんが、その時には学校や予備校の先生に採点や添削をお願いしましょう。
ポイントを押さえた学習
最後になりますが、古典は文法や単語などとは別にやっていたほうがいいものがピンポイントに存在します。そこらへんについて。
和歌の修辞法
古文で一つの壁になっているといってもいいのではないかというくらい得点差が出やすく、しかも頻繁に問題になっているのが、和歌です。
和歌には、枕詞などの修辞法を始め、形式分類など和歌独特の問題があり、どれも対策をしないと取りこぼす可能性があります。時間があればぜひ対策をしておきましょう。
文学史
文学史は、受験する大学によって出題するところとしないところが分かれます。自分の受ける大学によって必要なら勉強しておきましょう。
よっぽどでない限りは上に挙げたように古典常識の本などで取り扱っている範囲の学習で十分です。個別に対策しておきたいのなら上にあげたようなものみたいなのがおすすめです。
吉野式スーパー古文敬語
多くの受験生が苦手としているのが、この「敬語」です。
古文の敬語は、主語を判断したり訳したりするときにとても重要になってきます。敬語ができないと、誰が、誰に向かって喋っているのかわからないのです。
なので、問題になりやすく、そしてニガテな人も多いです。他の全てができても、敬語だけできないとボロっと点を落としてしまうことも…
そういう人や、敬語で点数を落としたことがある人におすすめなのが、この「吉野式スーパー古文敬語」です。
長さはそこまでないので、1週間もあれば1周できてしまいます。
不安を残すくらいだったら、この1冊をやり遂げて入試本番を向かえるようにしてください!
得点奪取古文 (記述対策)
国公立とセンター試験の違い、それは記述があるかないかです。
この記述というのは少し特殊、というかやはりマークとは全然違うので対策をしておいた方がいいと思います。
特に、国公立や私立のハイレベルになると差がついてくる問題はやはり記述です。
他の記述対策の参考書と同様に自己採点しやすいように祭典の基準が明確で、独学しやすくなっています。
レベル的にも早慶・難関国公立あたりにはちょうどいいと思うので時間がある人はぜひ手を出してみてください!
あさきゆめみし (漫画)
最後は、漫画です!
古文が苦手で、どうやって勉強したらいいのかもわからず途方に暮れている人もいるかもしれません。
そうした人にぜひぜひおすすめしたいのが、この漫画です!
僕は、日本史のテストが本当に嫌で(というか、漢字の人物覚えるのが苦手で) 、漫画で全部押さえた経験があります。
漫画はパラパラ読めるし、意外なところで役に立つ知識も拾う事ができます。
もちろん、漫画さえ読めばいいなんてことは言いませんが、スタートのきっかけくらいにはなると思います。
最後に:古文を得点源にしよう
以上が、センター ~ 難関大学までの 古文のおすすめの問題集、参考書でした。使ってみたいと思ったもの、これをやってみようと思うものはありましたか?
試験までに時間があるのなら、まずはどれか1つ手にとってやってみるといいと思います。そのうち、合う・合わないの感覚がわかってくると思うのでそうしたら別のに乗り換えるのがいいでしょう。
勉強で大切なのは、自分にあった参考書をしっかりつやりこむことです。いいなと思ったものが見つかったらそれをとことんやりこむと成績もぐんぐん上がっていきますよ。
また、関連記事に大学受験で僕が使ってきたオススメの参考書をリストアップしてみたので、ぜひ参考にしてみてください!
関連記事:【大学受験】京大生ブロガーが選ぶおすすめの参考書まとめ